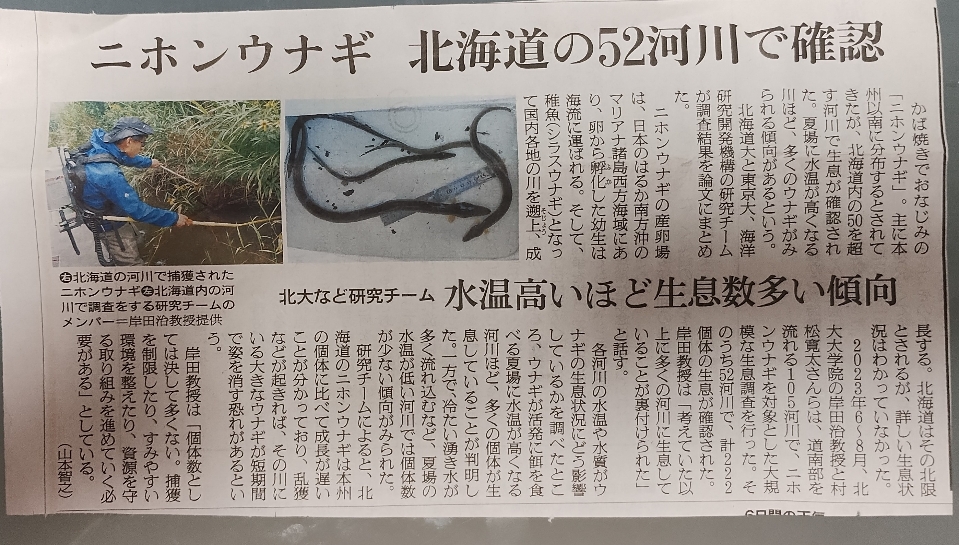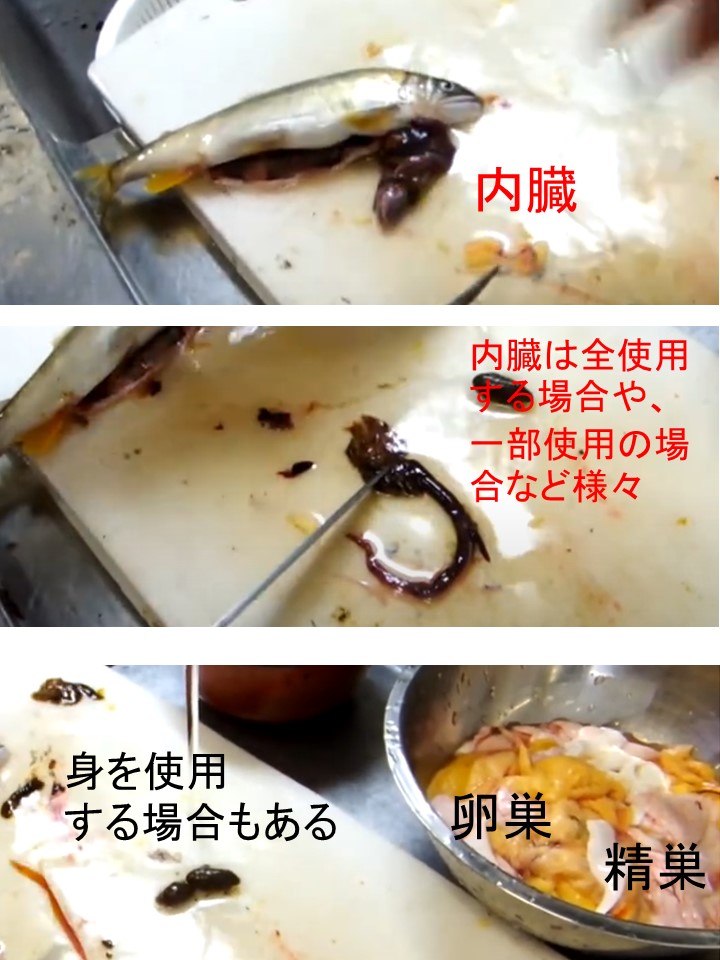「御漁場」(長良川の鵜飼いは唯一皇室の漁場となっています。詳しくは弊社サイトに記載)と聞くと、どこか格式ばった印象を持たれるかもしれませんが、そこに立つ“人”──鵜匠の存在は、実にドラマチックです。
長良川の鵜飼で使われるのは、夜。松明をたき、川面に火のゆらめきが映る幻想的な空間。そこに黒ずくめの装束をまとい、舟の上に立つ鵜匠の姿は、古典絵巻そのもののようです。
実はこの衣装、ただの演出ではありません。鵜匠が着ているのは、伝統的な「狩衣(かりぎぬ)」と呼ばれる装束で、平安時代から続く宮中儀礼に由来するもの。黒を基調に、腰に編んだ“腰蓑(こしみの)”を着け、頭には「烏帽子(えぼし)」をのせる──これらすべてが、“宮内庁式部職”としての礼法に則った正式な装束なのです。
(写真出典/ぎふ長良川の鵜飼ウエブサイトより)
ではなぜ“黒”なのか? それは、夜の漁において光を反射せず、魚を驚かせないためといわれています。また、夜の川に身を溶け込ませることで、鵜やアユの動きを繊細にとらえることも可能に。**目立たないことが、もっとも目立つ技になる──まさに「静かなる匠」**の世界です。
鵜匠の動きにも、所作の美が宿ります。舟の上での一挙手一投足は、長年の鍛錬と川への敬意から生まれるもの。決して派手ではないその動きが、鵜と阿吽の呼吸で連動し、瞬時にアユをとらえる──この洗練された“技”こそ、御漁場の象徴でもあるのです。
私たち毎日SPCでは、このような“川文化”の背景を大切にしながら、アユという魚の価値を未来へつなぐよう努めています。魚そのものだけでなく、それを取り巻く人・風景・儀礼にまで目を向けることで、より深く、より誇りをもって、この仕事に取り組めると感じています。
もし長良川の鵜飼の動画や写真に出会うことがあれば、ぜひ「なぜ黒い服なのか?」という視点で見てみてください。そこには、静かに受け継がれた1000年の知恵が詰まっているのです。
鵜飼のことを詳しく知るには、「ぎふ長良川の鵜飼 公式サイト」をお勧めします。